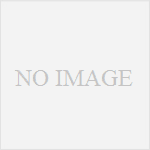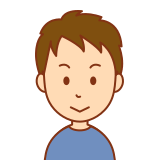
この人はどんな人なの?
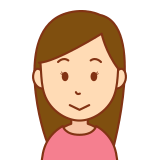
八王子・生活者ネットワークから出馬する新人よ。小さな声に耳を傾ける政策を中心に福祉や食に関しての取り組みに興味があるようね。学生時代カリフォルニアにホームステイ中ハンバーガーの美味しさに感動して移住を決意したらしいわよ。
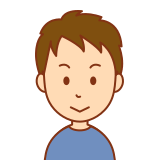
分かる。日本のとは全然違うもんねー
玉正 さやか さんの紹介
2000年
高校在学中にホームステイで訪れたカリフォルニアで人種の多様性と自然の豊かさとハンバーガーのおいしさに感動する。そして移住を決意。
2006年 カリフォルニア州 サンタモニカカレッジ卒業
米国で生活する中で多様な人がお互いを認め合いながら生活することのすばらしさを感じる。また、誰もが気軽に政治について話し合っていることに感銘を受ける。
その後、カリフォルニア州美容師免許を取得し美容室に勤務
帰国後、翻訳業務に従事。
2013年
第一子出産を機に、自然豊かな土地で子育てをするために八王子市・高尾に転居。
仕事をしながら子育てをする中で、家族だけではなく、地域のつながりの中で子どもが成長していくことの重要性を実感する。
2018年
生活クラブ生協 勤務
福祉事業に携わり、地域福祉の重要性を感じる。
2022年 八王子・生活者ネットワーク 政策委員 自然が豊かな環境の中で子育てをしたいと考え、第一子出産後八王子に引っ越してきました。現在は子育てをしながら働いています。
八王子で生活する中で、福祉や環境、食についてもっとこうなったら良いなと感じる場面が増えてきました。
一人ひとりの生活者が安心して暮らしていくためには、生活者の意見に基づいた街づくりが必要です。それを実現するには、生活の中で感じる小さな疑問や課題を、地域のみんなで話し合いながら、地域で決めていくような仕組みが求められます。
「小さな声に丁寧に耳を傾ける」
これを出発点に市民に寄り添った政策をすすめていきます。
そして、一人ひとりの個性が尊重され、多様性を認め合い、協働しながら暮らしていける地域づくりを目指します。 生活者ネットワークが掲げる、一人ひとりが大切にされるまちを実現するために、私は、この八王子で、赤ちゃんから高齢者まで、どんな状況にある人も、誰もが安心して暮らし続けることができる地域づくりを 市民が主体となってすすめることを目指します。
長引くコロナの影響や物価の高騰により、生活への負担が増している人が多いのではないでしょうか?
とりわけ、ひとり親世帯、非正規で働く方やその子どもたちへの影響は大きいと思います。
家計や学費のためにアルバイトをする学生、親の負担を考慮し、習い事を我慢する子どもたち、家計の負担軽減にため娯楽を諦めるなど、表からは見えなくとも、実際に生活に困難を抱えている家庭はたくさんあります。
そんな中、困難な状況にあっても声をあげることをためらう当事者がほとんどです。
経済的に困難を抱える世帯がどんな状況にあるのか、また、コロナの感染症拡大が生活にどのような影響を与えているのか、実態を把握することが必要です。
そして、就労支援や居住支援、食の支援や子どもたちへの支援など、実態に合わせた適切なサポートが大切です。
八王子においては、そのような支援に取り組む市民団体(民間の団体)がたくさんあります。そのような団体と行政がしっかりと連携し財政面を含め必要な支援がしっかりと行えるような取り組みを考えていくことが必要です。
誰もが安心して生きていく権利があります。
安心して生きていくための暮らしを保証するために、誰一人として制度からこぼれおち、社会的困窮を深めることがないよう、丁寧な情報発信を行うとともに施策の充実をめざします。
高校在学中にホームステイで訪れたカリフォルニアで人種の多様性と自然の豊かさとハンバーガーのおいしさに感動する。そして移住を決意。
2006年 カリフォルニア州 サンタモニカカレッジ卒業
米国で生活する中で多様な人がお互いを認め合いながら生活することのすばらしさを感じる。また、誰もが気軽に政治について話し合っていることに感銘を受ける。
その後、カリフォルニア州美容師免許を取得し美容室に勤務
帰国後、翻訳業務に従事。
2013年
第一子出産を機に、自然豊かな土地で子育てをするために八王子市・高尾に転居。
仕事をしながら子育てをする中で、家族だけではなく、地域のつながりの中で子どもが成長していくことの重要性を実感する。
2018年
生活クラブ生協 勤務
福祉事業に携わり、地域福祉の重要性を感じる。
2022年 八王子・生活者ネットワーク 政策委員 自然が豊かな環境の中で子育てをしたいと考え、第一子出産後八王子に引っ越してきました。現在は子育てをしながら働いています。
八王子で生活する中で、福祉や環境、食についてもっとこうなったら良いなと感じる場面が増えてきました。
一人ひとりの生活者が安心して暮らしていくためには、生活者の意見に基づいた街づくりが必要です。それを実現するには、生活の中で感じる小さな疑問や課題を、地域のみんなで話し合いながら、地域で決めていくような仕組みが求められます。
「小さな声に丁寧に耳を傾ける」
これを出発点に市民に寄り添った政策をすすめていきます。
そして、一人ひとりの個性が尊重され、多様性を認め合い、協働しながら暮らしていける地域づくりを目指します。 生活者ネットワークが掲げる、一人ひとりが大切にされるまちを実現するために、私は、この八王子で、赤ちゃんから高齢者まで、どんな状況にある人も、誰もが安心して暮らし続けることができる地域づくりを 市民が主体となってすすめることを目指します。
長引くコロナの影響や物価の高騰により、生活への負担が増している人が多いのではないでしょうか?
とりわけ、ひとり親世帯、非正規で働く方やその子どもたちへの影響は大きいと思います。
家計や学費のためにアルバイトをする学生、親の負担を考慮し、習い事を我慢する子どもたち、家計の負担軽減にため娯楽を諦めるなど、表からは見えなくとも、実際に生活に困難を抱えている家庭はたくさんあります。
そんな中、困難な状況にあっても声をあげることをためらう当事者がほとんどです。
経済的に困難を抱える世帯がどんな状況にあるのか、また、コロナの感染症拡大が生活にどのような影響を与えているのか、実態を把握することが必要です。
そして、就労支援や居住支援、食の支援や子どもたちへの支援など、実態に合わせた適切なサポートが大切です。
八王子においては、そのような支援に取り組む市民団体(民間の団体)がたくさんあります。そのような団体と行政がしっかりと連携し財政面を含め必要な支援がしっかりと行えるような取り組みを考えていくことが必要です。
誰もが安心して生きていく権利があります。
安心して生きていくための暮らしを保証するために、誰一人として制度からこぼれおち、社会的困窮を深めることがないよう、丁寧な情報発信を行うとともに施策の充実をめざします。